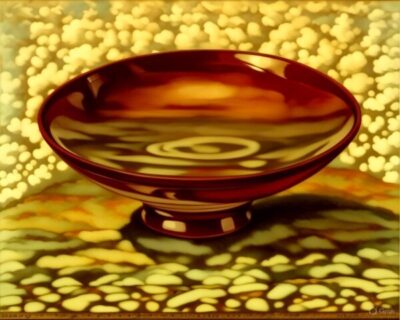昨日はお隣になった方が歯医者さんでした。歯がピカピカで綺麗だった反正天皇の話題が出ました。 そんなことを思っていたら今日の朝活はこの水歯別命(ミズハワケノミコト→後の反正天皇)のところを読むことになりました。 このエピソードは『古事記』『日本書紀』ともに大筋違わず掲載されていています。 イザホワケ皇子(後の履中天皇)が...
森澤勇司の記事一覧( 32 )
毎週、日曜日7:00から『日本書紀』の完読会をclubhouseで開催していただいてます。 日本の正史とはいいながら『古事記』にくらべ少々マイナーな『日本書紀』日本人で通読にチャレンジしようという方々が集まる貴重な時間です。 本日のテーマは天孫降臨でした。 この中で登場するのが日本の最重要神勅と言われる「天壌無窮の神勅...
新月は満月のこと 今日は頭が混乱する言葉の交錯をテーマにすることにしました。 朝活の話題から連鎖してイメージが湧いてきました。『聖書』は常夜灯の話題。『源氏物語』平安時代の通夜の話がでました。 自分の課題も宇宙の話が出てきたので暗い夜に見える星空をイメージしていました。 カレンダーを見たら今日は旧四月二十七日、 5月2...
現在、「平和(へいわ)」は地球上のすべての人が望んでいるよい意味で使われる事が多い言葉です。 この「平」と「和」の漢字のつらなりは『古事記』に度々登場します。この「平和し(やわし)」について集めてみました。 🙆♂️天孫降臨の前に葦原中国(アシハラナカツクニ)を...
じゅごんとアシカ 今日はイメージするものと現物の違いについてです。 じゅごんとアシカ 朝活で『源氏物語』『日本書紀•古事記』『聖書』を読んでます。 海がわれる場面だけが有名な「出エジプト記Exodus」に主がモーセに天幕建設の指示を与える場面があります。 「主はモーセに仰せになった。 イスラエルの人々に命じて、わたしの...
秘伝書が伝える心の病 少し調子悪かったので「病」について書き残してある本を開いてみました。 幸正能(まさよし) 天文8年(1539)ー寛永3年(1626)年、享年88歳 当流の2代目、37歳の時、足利義昭の意向で安芸国に出向し毛利輝元の小鼓指南をした 能楽師小鼓方 当時としては長生きです。昔は平均寿命が短いので日本人全...
技術×やる気→自分の立ち位置 今日は朝から体調不良、、 そのまま舞台に行きたんたんと勤めました。午後の予定はキャンセルして休んでました。 やろうと思ってできない時や、ここっていう時にこけたりすると「つかえない!!」という言葉がネオンのように浮かんできます。 いまは直接は言われなくても思われてること多いかもなぁ かつては...
人の批判の背景 明日、能「氷室」という氷がテーマの曲を勤めます。氷室神事や『源氏物語』『枕草子』の氷関連のところを読んでみると、、 やはり人は人の批判が気になるものなのか 紫式部が清少納言のことを語っているところを発見💡 じゃあ逆はないのかと思って見てみると清少納言は紫式部の夫の事をいろいろ書いている。...