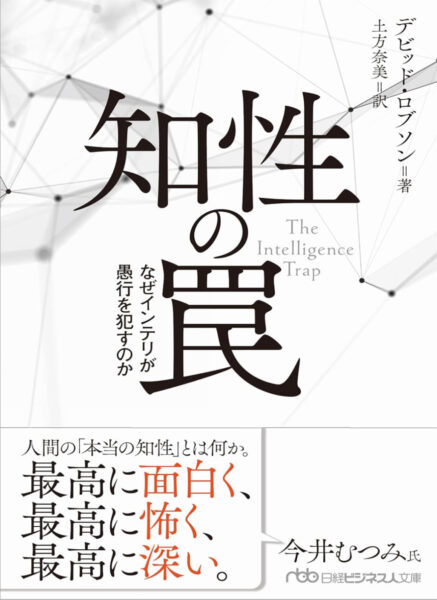条件が揃っていても実現しないこと【実朝】
昨日「知性の罠」を読みました。エジソンやコナン・ドイル、レイ・クロックなど日本でも有名な人物のエピソードから認知バイアスのことが語られています。最近読んだ本の中でもおすすめの一冊です。
この本を読んで頭に浮かんできたのが鎌倉三代将軍であり28歳で暗殺された源実朝のエピソードです。これは新作能のなかでも上演頻度が高い古典のレパートリーになりつつある一曲です。
「大海の磯もとどろによする浪われて砕けて裂けて散るかも」という和歌が現代にも伝わっています。

「この由比の浜に浮かめんと。宋人 陳和卿の指図にまかせ。監臨の奉行、数百輩、筋力を盡しおし曳くといへども。いはほのごとく寸尺も動くことなし大船は。いたずらに砂頭に朽ち損じて。渡宗のこころざしもついに空しくなる」

源実朝が建保4年(1216年)に宋人・陳和卿に命じて建造した巨大な唐船は、彼の渡宋計画の象徴であります。『吾妻鏡』によれば由比ヶ浜で進水に失敗し、砂浜に沈んだとに記される。動いたかどうかはともかく巨大な船は海の上で使い物にはならなかったのです。
実朝の動機は、陳和卿による「前世は医王山の長老」との言葉によるものでした。いわゆる背中を押された状態と言ってもいいかもしれません。
権力もあり財力もあり協力者もいる、リーダーシップもあり船は完成するものの、、やろうと思っていたことは実現できない。不思議ですね。
私自身は能舞台で学んだことや日本の文化についてこれからも出版に取り組んでいきたいと思っています。そういう時に出逢う方の中にも社会的な立場もあり協力者もたくさんいるリーダーシップもあるそれでも本が出ない。やはり自分より条件がいいのになぜ何年も進まないのだろうと不思議な感じがすることがあります。

鶴岡八幡宮の実朝暗殺の現場になった大銀杏は2010年強風によって倒れてしまいました。現在は二代の銀杏が元気に育っています。
長い目で見れば造船の失敗ものちの造船のための教訓となります。とはいえ自分の夢は生きているうちに叶えたいことも多いです。
「あなたは休暇の目的地へ、あと半分のところまで運転してきた。自分だけの時間を過ごすことが旅の目的だ。しかし体調が悪く、今では自宅で週末を過ごしたほうが良いのではないかという気がしている。家で過ごすほうがはるかに良いので、すでに半分まで運転してきてしまったのを非常に悔やんでいる。」『知性の罠』より
サンクコストがあると人は正常な判断ができなくなります。またこのような記載もありました。
「日本語には、初心者の好奇心や新たなアイデアに開かれた姿勢を表す「初心」という言葉がある。禅僧の鈴木俊隆が1970年代にこう語っている。「初心者の心には可能性があります。しかし、専門家といわれる人の心にはそれはほとんどありません」『知性の罠』より
この防止策が世阿弥が語る「初心忘るべからず」に通じていくんだなぁ。この2冊あわせて読むと課題と解決策の組合せになります。
何事においてもバランスを欠いた巨大な部分があると思った方向に進まなくなります。目指す方向にそった学びの時間は必要ですが100%になってしまったら学ぶことが目的になってしまいます。楽器の練習で実技だけで音楽理論が全くわからないのはどこかで伸び悩みます。だからと言って音楽理論だけ学べば楽器が弾けるようになるわけではありません。
自分の願望実現も学びが多過ぎて海に出せない船のように砂浜で朽ち果てることのないよう新鮮な志で取り組んでいきたいですね。
「大海の磯もとどろによする浪われて砕けて裂けて散るかも」源実朝
最新記事 by 森澤勇司 (全て見る)
- 和歌の世界と天文学 - 2026年2月14日
- 40年ぶりのファウスト - 2026年2月12日
- 和歌に詠まれた景色 - 2026年2月6日
- 『酸模』 - 2026年1月30日