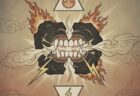能と『易経』
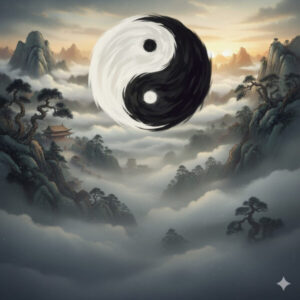
朝活は『春秋左氏伝』『日本書紀』孝徳天皇『聖書』Genesis
今日は『左伝』『日本書紀』共に『易経』の引用がある場所でした。
ーーーーーーーーーー
『春秋左氏伝』荘公二十二年(紀元前672)
陳候が敬仲について筮を立てさせたところ「観」の卦が「否」の卦に変ずるとでて次のように判じた。
「国の光を観る、王に賓たるに用ふるに利し」
このかたはきっと陳にかわって国をもたれるでしょう。この土地ではなく他国で、本人ではなく子孫が。それは光は遠方から輝いてくるものだからです。
ーーーーー
このあと易占の読み解きが語られる場面です。
この「観」の四爻は「観光」の語源にもなっているので384ある爻のなかでも広く知られています。
この時の占い方がよくわかります。
紀元前の易占が現在まであまり変わっていないことが驚きです。読み解きの具体例があり面白い記述です。
ーーーーーー
『日本書紀』
易に曰へらく『上を損して下を益す。節ふを制度を以てして財を傷らざれ。民を害はざれ』といえり
ーーーー
こちらは風雷益からの引用です。身分の低い人を率先して豊かにするような象徴です。
『日本書紀』では占いではなく慣用句として引用されています。
昨今は『易経』の本も人気で種類が多くなりました。ほとんどは占いか教訓的な卦の解釈が多いように思います。
日本では「大化」から「令和」まで250ある元号の一割以上『易経』由来のものがあります。「明治」も「大正」も『易経』由来です。
神社や日本の伝統文化に『易経』はかなり深く関わっています。お米と水のように融合しているので『易経』だとも思わないくらい染み込んでいる。
能と『易経』の関わりも多数あります。わかりやすい一例は歌舞伎「勧進帳」の原曲、能「安宅(あたか)」の最後「虎の尾を踏み」という言葉です。
これは「履」卦の四爻「履虎尾。愬愬終吉」
「虎の尾をふむ。さくさくたれば終に吉」という爻辞の由来です。
危険な目に遭うが助かるという意味です。
物語のあらすじも「履」卦の爻辞にそっている流れです。
その外、『易経』と深く繋がっているとおもわれる作品は下記です。
「羽衣」「天鼓」「善知鳥」「大原御幸」「柏崎」「阿漕」「葵上」「実盛」、、、、まだまだいろいろあります。
易の爻辞とあらすじ、使われている単語など、、『易経』の爻辞を骨組みにして物語を作ったのか。たまたまの偶然なのか。
こういうものはこじつけ解釈はよくないのですが共通点は多いものです。
※画像はAIで生成しました。
※日本文化の土台としての『易経』は月三回ほどズームで開催してます。
最新記事 by 森澤勇司 (全て見る)
- 和歌の世界と天文学 - 2026年2月14日
- 40年ぶりのファウスト - 2026年2月12日
- 和歌に詠まれた景色 - 2026年2月6日
- 『酸模』 - 2026年1月30日