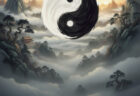『易経』と日本の文化
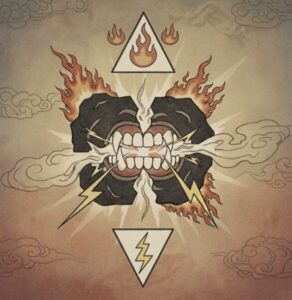
『易経』と日本の文化
朝活は『続日本後紀』仁明天皇、『日本書紀』継体天皇、『聖書』Genesis
『続日本後紀』には空海と東寺の記述が登場。かなり大規模な予算を取って国家の祈祷をする件。現代だったら税金で認められるかなぁと思いながら読み進める。
そこで少々難解な『易経』の記述がありました。
ーーーーーーーーーーー
承和二年正月二十二日
新銭を鋳造することになり、次の詔を下した。
交易して有無を通ずる法は、中国古代の聖帝禹の発案に始まり、市での物々交換は易の⭕️「噬嗑(ぜいごう)」の卦から思いつかれた。
ーーーーーーーーーーー
『易経』は四書五経のひとつ『古事記』『日本書紀』にも濃厚に織り込まれています。ここはスルーされている現代語訳がほとんどです。
「噬嗑(ぜいごう)」の卦から物々交換の発想ができた??
発想というのは全く関連がなくても思いつくきっかけになることがあります。
それでもわざわざ記載してあるのであらためて「噬嗑」をみてます。
超ざっくりの意味は、口の中にものがはさまっていることから刑罰をはっきりと定めましょうという内容です。
ーーーーーーーーーー
『易経』噬嗑〔象伝]
雷(震)と電(離)のあるのが「噬嗑」である。古代の聖王はこの電光の明にのっとって刑罰則を明らかにし、雷鳴の威にのっとって、法令を整え正した。
ーーーーーーーーー
中にある六つの爻(こう)の内容は1行にすると下記のような内容です。
上 重い罪を改めようとしない
5 監獄を治める目的を達成し金を得る
4 硬い干し肉を噛むように困難を超えて金の矢を手にいれる
3 監獄を収めるが困難が伴う
2 看守の立場 罰が厳しすぎると自分を傷つける
初 足枷をはめめるような刑罰 立場も低いので大罪は犯せない
ーーーーーーーーーーーーーー
この卦をみて流通の仕組みを思いつくのが君子の視座とは感心します。
三爻あたりは労働の対価として金を得ると解釈すれば現代も変わらないですね。
喜びの対価というよりは我慢の対価というイメージを強く感じます。民の多くは働くことは苦役と感じていたかもしれないですね。
『易経』は占いのイメージが強いですが、日本の元号250のうち「大宝」「貞観」「天徳」をはじめ「明治」「大正」など『易経』を元にする元号は約一割です。
神社の方位盤や九星、音程なども『易経』由来のものが多く日本の文化の土台になっています。
能では「歌占(うたうら)」の台本に「命期、六爻の滅色なれば、、」とい『易経』の六爻にふれている言葉があります。
パッと手に入る『易経』の本は占い中心のものがほとんどです。日本の文化に関する読み解きは自分でしなければいけないのがまさに「噬嗑」であります。
※日本文化の土台としての『易経』講座は月に3回ほど木曜日20:00から開催してます。
※日本文化の土台としての『易経』本の企画書つくりました。想定読者 自分^^
※画像はAIで生成しました。
最新記事 by 森澤勇司 (全て見る)
- 和歌の世界と天文学 - 2026年2月14日
- 40年ぶりのファウスト - 2026年2月12日
- 和歌に詠まれた景色 - 2026年2月6日
- 『酸模』 - 2026年1月30日