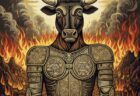新月は満月のこと?

新月は満月のこと
今日は頭が混乱する言葉の交錯をテーマにすることにしました。
朝活の話題から連鎖してイメージが湧いてきました。『聖書』は常夜灯の話題。『源氏物語』平安時代の通夜の話がでました。
自分の課題も宇宙の話が出てきたので暗い夜に見える星空をイメージしていました。
カレンダーを見たら今日は旧四月二十七日、
5月27日が旧五月一日朔(ついたち)です。
そこで今日は頭が混乱する言葉の交錯
まず明治の改暦以前の「新月」は「満月」をテーマにしました。
能の中でも度々引用される白楽天と呼ばれた白居易の漢詩があります。
「三、五、夜中(さんごやちゅう)の新月の色」
▶︎三、五は掛け算 十五夜のこと
その時に出る新月を読んだ詩です。
この「新月」は「東の空に上がってきた満月」のことです。
現在は「新月」といえば「朔(ついたち)」の月齢が約0の日を言ってます。
では現在の新月🌑を表す「朔(ついたち)」は月齢のことではなくカレンダーの月の初日「1日」を「ついたち」と言っています。
空の月の月齢に関係なく
カレンダーの1日を「ついたち→朔→新月🌑」といい、
改暦以前の「新月🌕」は「東に上ってきた満月🌕」の意味。
明治時代はよくも悪くもおでんをカレーにしちゃったくらいのインパクトがあります。さすが文明開化です。
戦前戦後はGHQ云々言う人がいたとしても文化の変化はビーフカレーをポークカレーにしたくらいの違いです。
文化の分岐点は様々ありますが、明治維新前後は日本語の概念も変えてしまうようなインパクトがあります。
同じように「すごい」も平安時代だったら「ゾッとする気味の悪さ」意味が今ではGreatの意味が一般的になりました。※一部今と同じ使い方もあります。
現在の「すごい人」はほとんど偉大な功績がある人の意味で使われます。
古語の意味で「すごい」だったら誰も見向きもしない落ちぶれた人という意味になる場合が多い。
今日は頭が混乱する言葉の交錯をテーマにしてみました。
言葉の変化も”すごい”ですね😃
※画像はAIで作りました。