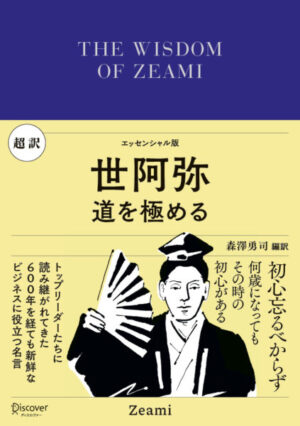牛若丸が手にしたもの
能「鞍馬天狗」に「この一大事を相伝する」という詞章がでてきます。能「張良」でも語られている黄石公から張良が相伝されたものを、鞍馬山の天狗が牛若丸に相伝する。幼少の時から絵本で牛若丸の話は読んでいたので能「橋弁慶」や「鞍馬天狗」は親しんだ物語です。
幼少期に読んだ絵本の物語を今は仕事で舞台に参加しているということを思ったときに何か大切なことを相伝されたということは判るのですが、肝心の「何を教わったのか」という中身を全く知らないということに気づきました。私の中では物語の知識は5歳から変わっていなかったのです。
何を相伝されたのか気になって調べてみると、実は太公望の教えをまとめた「六韜」が当時としては最高の兵法書だということがわかりました。能の物語としては「六韜」であるかはそれほど重要な事ではないので鞍馬天狗と牛若丸の関係をそれぞれの人の解釈で描くわけですが気になりはじめたことを止めるには読んでしまうに限ります。
能「張良」にも「鞍馬天狗」にも六韜の教えが反映されていないのか、そこが気になってきました。現時点(2018年4月26日)の時点では、張良が黄石公の靴を拾い上げる場面、牛若丸の稽古の際の天狗をまっていたという場面に六韜の教えが反映されているように感じてます。
国王であっても師と仰ぐ人を上座に座らせ、教えを請う準備をしてから質問の答えをもらうというところが守国で語られている場面を彷彿とさせます。
この太公望という人が親切だと思うのは、国王からの質問に対して、準備ができてないから教えないということではなく、「まず斎戒するように」という具体的な順番を明確に指示していることです。気がつくまで教えないと言うのは、本人の意識化に無いものは一生気がつかないで終わってしまうかもしれませんから素直に聞く国王とはっきり指示する太公望の信頼関係があって成立することだと思います。
紀元前の伝説と言ってしまえばそれまでですし、現代にも通じるというありきたりの言い方よりも、幼少期に読んだ絵本の主人公が手にしていた書物を読み解けることが自分にとっては一番興味深いことです。
最新記事 by 森澤勇司 (全て見る)
- 逆転の発想 - 2026年1月2日
- 2025年最後のチャレンジ - 2025年12月31日
- 今日の勉強部屋 - 2025年12月30日
- 『群書類従』届きました - 2025年12月29日