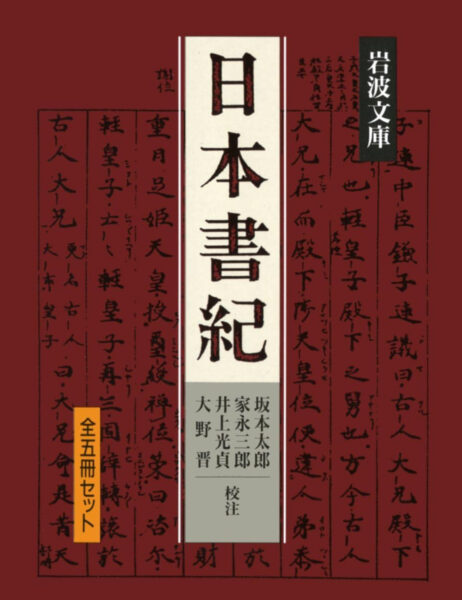4月8日 あっと驚く問題解決

4月8日は全国的にお寺の法要が行われます。そんな日の教訓として思い出すのはこの法要の始まった時に起こった出来事です。
推古天皇14年は西暦606年、丈六(5m弱)の仏像が作られる。丈六というのはこの時代、釈迦の身長は1丈6尺(16尺→約485cm)と言われていたので等身大像ということです。ネフィリムより大きいか^^
その仏像が完成した時、お寺の金堂の戸より大きくてどうにも入らない。
おおくの大工は「戸を壊して入れるしかないでしょう」という。
そこに鞍作鳥(くらつくりのとり)という名工がいて戸を壊さずに堂の中に仏像を安置させたという記録があります。
『日本書紀』によればその日、すぐに法要をしたそうです。
そして寺ごとに旧4月8日、旧7月15日(満月の日)に法要をすることになった。
日々、人が集まるとさまざまな問題が生まれてきます。その時に強引な多数決、強引な権力行使、戸を壊すような問題解決も時には秀れた方法と言えるかもしれません。
ところがスルッと「どうやったの?」という何もなかったかのようにニコニコと解決してしまう工もいるわけです。
私自身はどちらかというと戸を壊すよりも、、
めんどくさいから外に置いとけばいいんじゃないという放置の発想をする事があります。
キレでもかぶせといたら、、みたいな投げやりな時もあります。
納めるべきところにキッチリ納めると多くの人が笑顔になります。
自分ごととしてここを模索していくのも今生の課題ではないかと頭に浮かんできました。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
推古天皇
十四年(600年)の夏四月の乙酉の朔、壬辰の日。銅、繍の丈六の仏像、並びに造りまつり竟りぬ。
是の日に、丈六の銅の像を元興寺の金堂に坐せしむ。時に仏像、金堂の戸より高くして、堂に納れまつること得ず。
是に、諸の工人等、議りて日はく、「堂の戸を破ちて納れむ」といふ。然るに鞍作鳥の秀れたる工なること、戸を壊たずして堂に入るること得。
即日に、設斎す。是に、会集へる人来、勝げて数ふべからず。是年より初めて寺毎に、四月の八日・七月の十五日に設斎す。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
最新記事 by 森澤勇司 (全て見る)
- 部分と全体 - 2025年12月24日
- 試し酒 - 2025年12月21日
- 河豚とアヘン - 2025年12月20日
- リザーブストック15周年記念 - 2025年12月19日