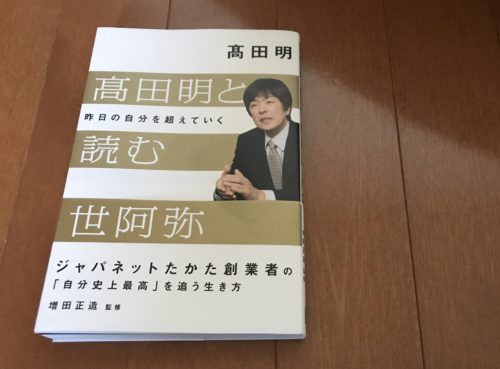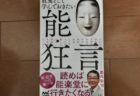舞台には自己肯定は必要か役に立つのか考えてみる
目次
人前に出ることの多い私にも自己肯定感は役に立つのか
能楽師 森澤勇司です。
今回のテーマは「自己肯定感」です。能楽師ですから舞台で人前に出ることは多い方だと思います。
最近よく耳にする「自己肯定感」ということについて興味がでてきたので本を読み始めています。すべての本をんではいないのですが10冊ほど自己肯定感に関する本を読んでみた感想を残しておこうと思います。
舞台ではほぼ意識していないものだった
さて自己肯定感とは何か。セルフアフォーメーションの訳なのでセルフが「自己」アフォーメーションは「宣言」とか「肯定」とかになるのでその「感覚」を「自己肯定感」という言葉で訳されています。
端的に言えば「感覚」です。絶対値のあるものではありません。簡単に言えば褒められれば上がる、けなされれば下がる、という感覚の一種です。
この自分以外の要因、他者からの影響で上がったり下がったりするわけですから、これを自分で評価しているのが自己肯定感です。
自分に対する自己評価の度合いを「自己肯定感」と定義して良いと思います。
自己肯定感はどんなときに必要なのか
自己評価が高い低いという観点で言えば、舞台では自己評価は高い方がいいと思います。ただ他者の評価は舞台が終わった後にはありますが舞台上にはありません。舞台に上がってから自己肯定感が上がったり下がったりするとしたらそれはかなり問題です。
実際、普段の生活で自己公的感が下がり気味になる方にとってはとても有効な方法が満載です。また稽古で思ったように出来なかったとき、日常生活でトラブルがあったときなど、自己評価が下がってしまうときまず自己肯定感を高めてから課題に取り組むのは有効です。
舞台で自己肯定感は必要か
結論を先に言うと自己肯定感は全くいりません。これは自己肯定感を否定しているのではありません。日常においてまた精神状態が気になるときには重要です。しかし、実際に舞台に上がるときに、自己肯定感、自己評価という尺度、物差しをもって舞台に上がることはリスクでしかありません。
舞台に自己肯定感が必要かと言われたら100%あり得ません。逆に自己肯定感0%でも最後までやりきると決めていることは必要です。これは無理して「私はできる」と言い聞かせるようなものではありません。自己肯定感と言うよりは自己定義と言葉の方が適切かもしれません。また自己肯定感は、自分以外の他者には肯定されないという前提があります。ですから「私はできる」「私はやる」などと自分を言い聞かせることを繰り返して気分をあげていくということが必要になります。
自己定義とは
私自身が自殺を考えていのちの電話で話を聞いてもらったときなどはまさにこの自己肯定感の奴隷でした。自分自身に自信が無い。他者からどう見られているかわからない。この尺度自体は私の救いにはなりませんでした。
他者から見ても自分自身もハッキリと否定できない自己定義、社会的定義と行ってもいいかもしれません。それは「私は森澤勇司である」「私は日本国籍を持っている」「私は男性である」「私は世田谷区出身である」「私は小学校を卒業した」「私は自分の名前を漢字で書ける」などなど、絶対に揺らがない事実の積み重ねの延長に「私は能楽師である」「私は羽衣の小鼓を打つことができる」など職業上のことを積み重ねていきました。そうしていると「私は出来る」という言い聞かせを自分が信じられるまで繰り返すと言うことは全くしなくなりました。
まとめ
まだまだ記しておきたいことは出てきますが、ここは自己定義についてのみ記しておきます。「自己肯定」と「自己肯定感」は別のことです。感覚は常に変わります。舞台や大切な人生の舞台に向かうときには、「自己定義」をさらにすすめて「社会的定義」を明確にすることが大事です。
自己肯定感を高める習慣は非常にいいと思います。なぜならば絶対的な自分への信頼感は習慣でつくられるからです。それなので瞬間的に高まるものではありません。そして他者の評価で簡単に上がり下がりしてしまいます。それなのでその物差しから解放されて揺るぎない社会的定義を明確にしてその中に自己定義を構築していくことが、自己肯定感を100%に保つ方法です。
最新記事 by 森澤勇司 (全て見る)
- 40年ぶりのファウスト - 2026年2月12日
- 和歌に詠まれた景色 - 2026年2月6日
- 『酸模』 - 2026年1月30日
- 資料の効率化とAI - 2026年1月22日