「大義」と「命」
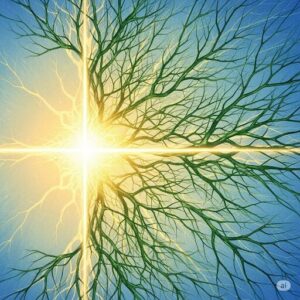
100日チャレンジ100日目
「大義」と「命」
チャレンジの内容は「本の執筆」のために「ブログ100記事」にしてみました。
まずは自分の中にどんなものが入っているのか、押し入れの中を全部出すくらいの感じでやってみました。
毎日、その日に浮かんできたお題にしているので100日目にどんなことが思い浮かぶのか楽しみにしていました。
そして昨日、ちょっと戦前戦後の事がモヤっと浮かんできてましたがハッキリしてませんでした。
そんなとき昨日の出版記念講演会でお隣になった方のFacebookを見てみると旧GHQ本部だった場所のレストランで食事をしている記事がありました。そしていいねが99。ポチッとしたら100になりました。
という事で戦前戦後の事を100日目のテーマにしてみます。
広告でもGHQが消した日本人の〇〇、とか洗脳されてる、神道を無くそうとした、墨塗り教科書などなど、、、都市伝説的煽り記事が出てきます。
多くが元情報の曖昧なものなのでGHQがどうしたこうしたはともかく、戦前戦後で大きく変わった一点があります。
それは、、、
「自分の命を尊重する事」
「命を大切にしよう」という価値観です。
先祖や親からいただいた命を大切にすることに違和感を抱く人は少ないと思います。
⭕️何よりも大切なのは「命」という価値観こそが戦後の日本人の最大の変化です。
じゃあそれまでは命以上に大切なものがあったのか??
それは「大義」です。大義のためなら命は軽い。
「家」を守る、名誉を守るため「命」を投げ出しても「大義」を守る。
「大義」という「何のために」を「命」を捨てても守る価値観がありました。
これが「命」が最重要に変わった。
神社がどうの神話を教えないという表面的は話は講演会でもよく話題になります。大切なのはそんな表面のことではありません。
能の中にもそうした価値観が濃厚に描かれているので3箇所ご紹介します。
—————————
▶︎能「海人(あま)」
志度寺縁起をもとにした能
藤原不比等の子を産んだ海人が、子を後継者として認めてもらうために命をかけて海の中に落ちた宝を取り戻しに行きます。
「その時、海士人(あまびと)申すやう。もしこの珠を取り得たらば、この御子を世継の御位になし給へと申ししかば、子細あらじと領状し給ふ。⭕️さても我が子ゆえに捨てん命、露ほども惜しからじと、、、、」
▶︎能「屋島」
屋島の戦で義経が海に弓を落としてしまう。義経は体が小さかったので「敵の大将はチビだ!」と言われないために船を飛びこえ落とした弓を取りに行く場面。
「弥猛心の梓弓、敵には取り伝えじと、惜しむは名のため、⭕️惜しまぬは一命なれば、身を捨ててこそ後記にも佳名を留むべき弓、筆の跡なるべけれ」
▶︎能「谷行」
山伏修行で調子が悪くなった仲間を谷に投げ捨てる事を告げる場面。
「いかに松若、確かに聞け。この道に出でて、かやうに違例する者をば、谷行とて忽ち命を失う事。これ昔よりの大法あり、、、」
———————
能には現在のようにまず命を大切にしようという価値観では成立しない話が多く現存しています。
場面は違いますが、全て守るべき「大義」のためなら命は捨てても惜しくないという価値観が描かれます。
明治から昭和初期までの国民の大義は「天壌無窮の神勅」です。神社本庁の読み下しは原文と違うので下記に原文掲載しておきます。
「葦原千五百秋瑞穂国、是吾子孫可王之地也。宜爾皇孫就而治焉。行矣。宝祚之隆、当与天壌無窮者矣」
全て働くのも勉強するのも全ては天壌無窮の神勅という「大義」のため
「大義」と「命」
どちらが大切なのか、戦前戦後に占領軍が云々という事を語る方は「大義」に生きる覚悟があるのか決めてから発言するのがおすすめです。そうしないとただの都市伝説みたいに聞こえちゃいます。
飛行機に乗ってもまず自分の命を確保する事がアナウンスされます。これがいけないと言えるのか?
戦前戦後の価値観の違いは「大義(何のために生きるのか)」それがなくても「(命)まず生きる」を最優先するのか。
100日めはそんな事が頭に浮かんできました。
※画像はAIで生成しました。
100日チャレンジ2チームめは今日で45日め、ブログはあと55日続けます😃








