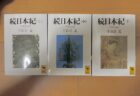氏と姓の謎

氏と姓の謎
朝活は『日本後紀』桓武天皇、『日本書紀』安康天皇、『聖書』Genesis
読み始めの時期が違う書物ですが、似たような記述が重なるのはいつも不思議に思います。今日は氏と姓
今日も言葉と意味が交錯する頭の混乱するテーマです。
———————-
『日本後紀』桓武天皇(口語訳)
延暦十四年(795)十一月十五日
天皇が次のように詔した。
薬師寺の賎身分から解放されて良身分となった者が、朝臣、宿禰、臣、連などの「姓」を申請する事を一切禁止する。みな「氏」名の下に部の字をつけよ。
————————-
そもそも日本では「姓」は立場を表すもので現在はありません。
氏が苗字
「姓名」と書いてあったら苗字と名前を書きます。
この姓はそもそも現在にはないので「氏名」ですが、細かいことはともかく何を記載するかはわかるので特に疑問にも思わず過ごせます。
この身分を表す「姓」は申請しちゃダメというルールの記載です。その代わりに「〇〇部」という氏にしなさいとなります。
そのあと
—————
延暦十五年(796)三月十五日
唐人に姓を賜った。
——————
なんと!外国人には「姓」を賜る!
それ相当の身分の人だったかもしれません。
「姓」事件はたびたび起こっています。
一例では允恭天皇の時代には大規模な氏姓の修正がありました。
—————————
允恭天皇四年(415)九月九日
上古治むること、人民所を得て姓たがふ事なし
今、朕、践祚りてここに四年、上下相争いて百姓やすからず。或いは誤りて己が姓を失ふ。
或いは故に高き氏を認む。其れ治むるに至らざることは、けだし是によりてなり。朕、不賢しといへども、豈そのたがへるを正さざらむや。群臣、議り定めて奏せとのたまふ。
皆、言さく、「壁下、失を挙げまがれるを正して、氏姓を定めたまはば冒死へまつらむ。と奏すに可されぬ。
——————-
なにをしたかは↓にも
この時の問題はひとつの氏にバリエーションが増えていた事です。
百姓どころか万姓になってました。
そこで確認方法が決まります。
▶︎クカタチ
泥を鍋に入れて沸騰させ手を入れて中の石を探させる。
▶︎斧を火で焼いててのひらにのせる。
本当のことを言ってる人は傷つく事がなく、嘘をついていた人は火傷をする。
多くは火傷をしたとか、、、また勝手に姓を変えていた人たちはビビって列に並ばず訂正したようです。
昨今のSNSなりすまし問題にも近いものを感じます。
——————
実を得ざるものは皆傷れぬ。これをもって故に詐る者はおぢて、あらかじめ退きて進む事なし。これより後、氏姓を自ら定まりて更に詐る人無し。
————————
これだけ大変だった「姓」も明治時代に廃止になりました。
————
明治四年(1871)十月十二日に太政官布告
姓尸不称令
自今位記官記ヲ始メ一切公用ノ文書ニ姓尸ヲ除キ苗字實名ノミ相用候事
———————-
昨今、夫婦別姓という報道がされます。そもそも日本に別姓問題は存在しない。なぜなら「姓」はないからです。
源頼朝
氏→源
姓→朝臣
北条政子
氏→北条
姓→平
そもそも日本では姓廃止以前から夫婦別姓です。
現総理大臣の過去の動画を見ると「別氏」という言葉を使っています。
現代はどんな表記なのかみてみると
———-
民法
第750条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する
————
言葉はともかく「氏」と「姓」は混同されがちです。
中国語の「姓」は日本の「氏」の意味合いが強い。
江戸時代の「名字」も明治時代には「苗字」と表記されたり
現代は違う意味の言葉をマルッとひっくるめて「氏」「姓」「苗字」「名字」ほぼ同じ意味で使ってます。
「名」「名前」も下の名前とか森澤勇司だったら勇司の名前で使う事が多い。
法律を語る「別氏」も報道では「別姓」が一般的?
外国人が日本人のふりをすると批判される。反対に日本人も外国人のふりをして批判された人もいました。
何事も社会に対して嘘偽りはよくないですね。報道も正しい知識が得られるようにして欲しいものです。
※画像はAIで生成しました。