人の批判の背景

人の批判の背景
明日、能「氷室」という氷がテーマの曲を勤めます。氷室神事や『源氏物語』『枕草子』の氷関連のところを読んでみると、、
やはり人は人の批判が気になるものなのか
紫式部が清少納言のことを語っているところを発見💡
じゃあ逆はないのかと思って見てみると清少納言は紫式部の夫の事をいろいろ書いている。
清少納言は紫式部より少し年上。
『紫式部日記』の清少納言の批評がやけに印象に残りました。
出版の大先輩という観点でも作家批評は興味深い学びです。
ーーーーーーー
「清少納言こそ、したり顏にいみじう侍りける人。さばかり、さかしだち、真名書き散らして侍るほども、よく見れば、まだいと足らぬこと多かり。
かく、人に異ならむと思ひ好める人は、必ず見劣りし、行末うたてのみ侍るは。艶になりぬる人は、いと、すごう、すずろなる折も、もののあはれにすすみ、をかしきことも見過ぐさぬほどに、おのづから、さるまじくあだなるさまにもなるに侍るべし。
そのあだになりぬる人の果て、いかでかはよく侍らむ。」
ーーーーーーー
▶︎清少納言は得意になってとんでもない人ですね。頭良さそうにして漢字を書きまくってますが、よく見れば足りないところばかりです。
人と違ったことばかりしようとする人は必ず見劣りするものです。そして「異様さ」だけになってしまいます。
この後も続いていきます。読んでみると清少納言の批判というよりは紫式部の文筆ポリシーのようなものに読めてきます。
本人の自然な発見や気づきではなく、奇抜な変わった視点で差別化していくと初めはうまくいっても見劣りしてくると紫式部は語ります。
そして、奇抜さを求めるよう何なり世間とはずれていって「異様さ」だけが目立ってくる。
人と違っていたいと思って違いを求めた先に、周りから浮いてきて変人扱いされてくる。
ここだけ取り出すと清少納言が変人だと言っているようにも読めます。この章の最後に使用人の陰口を聞いてしまう場面があります。
「御前はかくおはすれば、御さいはひは少なきなり。なでふ女が真名書は読む。昔は経読むをだに人は制しき」
▶︎「奥様はあんなふうだから幸運が少なめですね。女が漢字の本を読んだりして、、昔はお経も止められていたものですよ」
それを聞いた紫式部は
「物忌みける人の、行く末いのち長かるめるよしども見えぬためしなり」
▶︎「縁起を気にしている人が長生きしたのなんて見たことないですよ」そう言い返してやりたいけど夫が亡くなった今、ほんとにその通りだなと思うのです。
あいつ変わったことして目立とうとして、、と思っていたら自分は普通に変わり者と思われていた。ショック大きいですね。
批判や悪口は、悪意とも見られます。その人の生きる指針や状況を知ってみると、そんなに腹の立つものでもなさそうです。
ーーーーーーーーーーーーーー
092 聞いていい批判、聞いてはいけない批判 表面的なことにはよく気がつくが、本質をよくわかっていない受け手がいる。また本質をよく知っているにもかかわらず表面的な技術を受けつけない者もいる。本質的なことと表面的な技術の両方をバランスよく見ることができる人物が、良い批評家と言える。 『花鏡』
『超訳 世阿弥』より
ーーーーーーーーーーーーーーー
最新記事 by 森澤勇司 (全て見る)
- 人の批判の背景 - 2025年5月19日
- ほんとに悪いヤツとは? - 2025年5月18日
- 毒親、親ガチャの顛末 - 2025年5月17日
- 今と昔の名前の違い - 2025年5月16日
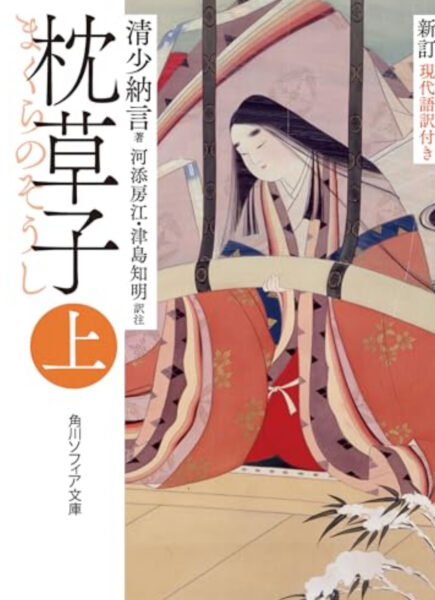
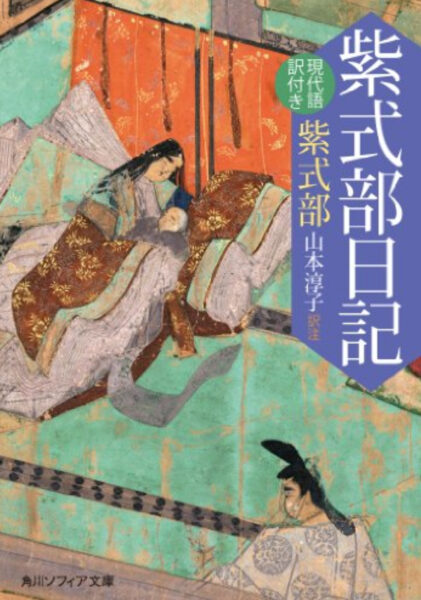

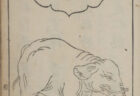
コメントを投稿するにはログインしてください。